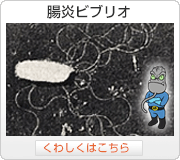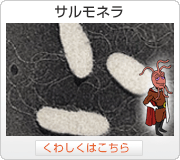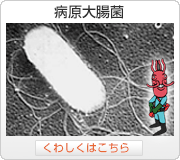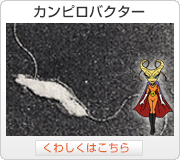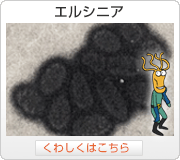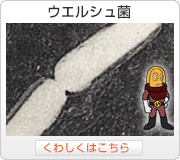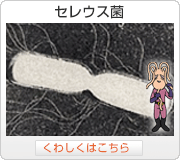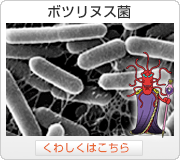微生物ラボ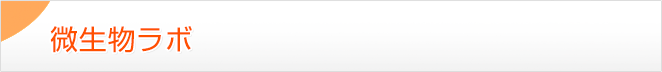
微生物の特徴
微生物は生態系の中で「分解者」の役割を果たし、動物や植物のつくりだす有機物を栄養源にして無機物(二酸化炭素と水)のほか、乳酸やアミノ酸などの有機酸やアルコールなどをつくりだします。
このような微生物を食品に利用することを「発酵」といい、多くの食品の製造にも利用されています。また、同じ作用により悪い物質がつくられることを「腐敗」とよびます。
微生物は分裂により増えますが、温度、湿度、栄養、pHなど、環境の影響を大きく受けます。これらの条件が整うと菌はどんどん増えていきます。

微生物の食品への利用
微生物を利用したさまざまな発酵食品は古くからつくられてきました。同じ原料でも発酵に使う微生物の種類によって、ちがう食品ができあがります。
微生物を利用してつくられた食品は、わたしたちの身近にたくさんありますので探してみましょう。
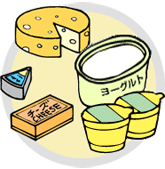
乳酸発酵
乳酸菌は糖を利用して増え、たくさんの乳酸をつくりだします。
乳酸がつくられると乳が固まり、そこからチーズやヨーグルトなどがつくられます。
また、乳酸菌には多くの種類があり、味噌やしょうゆなどの製造にも乳酸発酵が利用されています。

アミノ酸発酵
コウジカビにはデンプンを糖に、タンパク質をアミノ酸に分解する働きがあります。大豆や米をコウジカビにより発酵熟成させることで、さまざまな食品がつくられます。
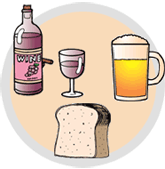
アルコール発酵
穀類や果汁に含まれる糖を酵母により発酵させるとアルコールがつくられます。
最近注目されているバイオエタノールも、発酵を利用して燃料となるアルコールをつくっています。
そのほかにもアルコール発酵が利用されています。パンをつくるときに、二酸化炭素をつくり生地をふくらませる役割もその一例です。
食中毒を引き起こす細菌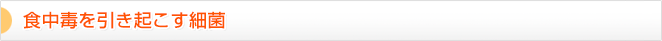
微生物のなかでも特に細菌は単純な単細胞生物で、短い時間で細胞が分裂して、どんどん増えていきます。微生物が増えるためには、まわりの環境(温度・湿度・栄養・pHなど)の影響を大きく受けます。
逆に環境を調整して細菌を増やさないようにすることもでき、食品を調理、保存するうえで食中毒を防ぐための重要なポイントになります。
細菌による食中毒(細菌性食中毒)は、2パターンの種類に分けられます。
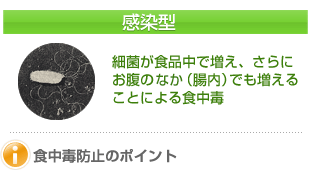
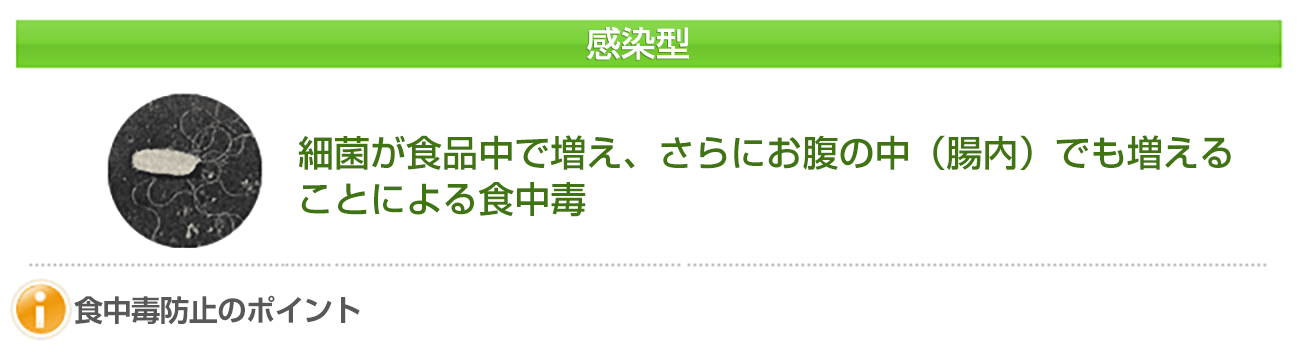
細菌は温度が高くなると増えてしまうので、冷蔵庫でしっかり冷やすことがたいせつです。ただし、冷蔵庫に入れることだけで食中毒を防ぐことはできません。
ほとんどの細菌は焼いたり煮たりするとやっつけることができるので、しっかり火を通すことによって防ぐことができます。
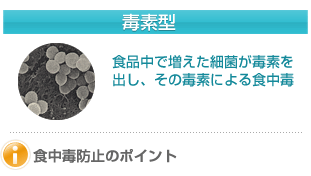
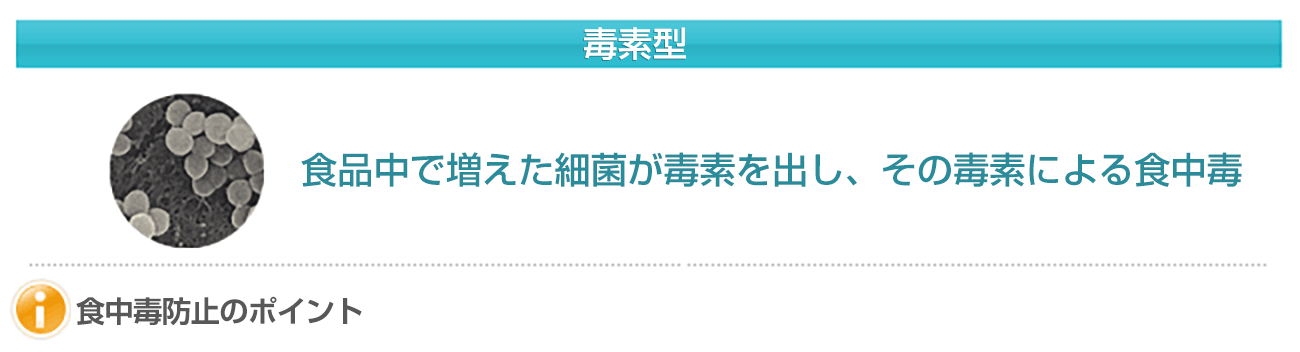
食品のなかで細菌がつくった毒素は熱に強く、高温で加熱しても毒素が残ってしまい、食中毒の原因になります。
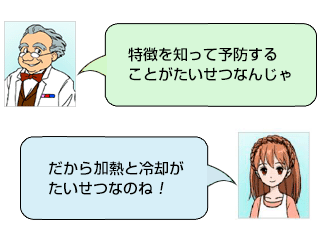
芽胞(がほう)菌
一部の細菌は熱に強いかたい殻(芽胞)をつくってしまうため、加熱してもこれらの細菌をやっつけることはできません。
芽胞は、加熱後に食品の温度が下がり始めると、菌の姿に戻り増えはじめます。これを防ぐためには、加熱後の食品を60℃以上で保温するか、短時間で10℃以下に冷却することが必要です。
食中毒を引き起こす細菌はさまざまな種類があり、それぞれちがう特徴をもっています。それぞれの細菌の特徴をよく知って食中毒を予防しましょう。
ウイルスによる食中毒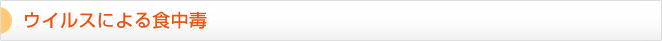
インフルエンザやノロウイルスなどの感染症は「ウイルス」が原因で起こります。ウイルスは、細菌の1,000分の1の大きさで、動植物の細胞に住み着いて増殖し、さまざまな症状を引き起こします。
食中毒の一つとして知られるノロウイルスは、ヒトの腸の中でのみ増えて、おう吐や下痢などを引き起こします。